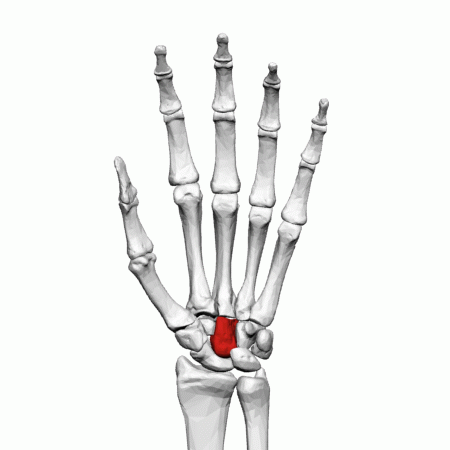
概要
有頭骨は手根骨の中で最も大きい骨で、手根中央部に位置します。近位列と遠位列の橋渡し構造を持ち、手の安定性と力の伝達に重要な役割を果たします。特に第三中手骨との連結が強固で、手の中心軸として機能します。
ランドマーク
付着する筋(起始・停止)
有頭骨には直接筋の起始・停止はありません。
構成する関節
- 有頭骨-舟状骨関節(近位)
- 有頭骨-月状骨関節(近位)
- 有頭骨-小菱形骨関節(橈側)
- 有頭骨-有鈎骨関節(尺側)
- 有頭骨-第二中手骨関節(一部)
- 有頭骨-第三中手骨関節(主なCM関節)
関連する靭帯
- 掌側手根間靭帯
- 背側手根間靭帯
- 有頭骨-第三中手骨靭帯
- 有頭骨-月状骨靭帯
- 有頭骨-有鈎骨靭帯
隣接する骨
触診ポイント
- 手背中央で最も突出を感じやすい:第三中手骨基部をたどると、近位方向の窪みの先に有頭骨が触れやすい。
- Lister結節と第三中手骨基部を結ぶライン上:その中心部の深部に位置。
- 手関節の屈伸で動きはわずか:周囲の骨と強く連結しているため可動性は少ない。
- 押圧で軽い圧痛が出やすい:特に過使用や手根骨アライメント不良時に反応が出る。
東洋医学的関連
有頭骨は手の中央軸に位置するため、以下の経絡と関連づけて考えることができます。
0 件のコメント:
コメントを投稿